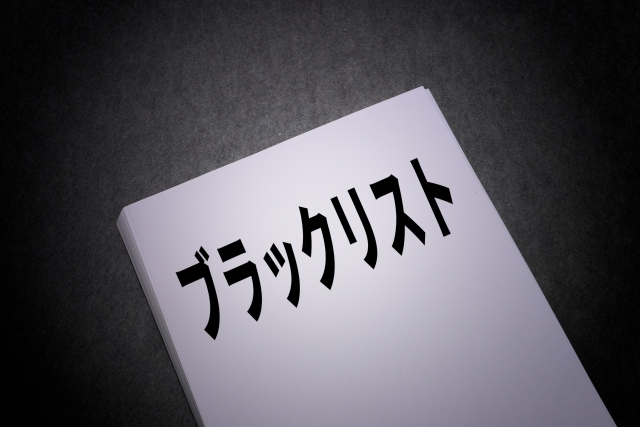こんにちは、借金トラブル119です。
私たちの生活やビジネスにおいて頻繁に使われる「ブラックリスト」という用語は、厳密に言うと実在しません。
「ブラックリストに載ると信用がなくなる」という言葉を耳にしますが、一体どのような影響があるのでしょうか。
ブラックリストの実態や仕組み・背景について、正しい情報を知り得ない方も多いはず。
そこで本記事では、ブラックリストの定義や掲載条件を解説します。
ブラックリストが使用されるときや、もたらす影響も解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
ブラックリストとは何か?基本的な定義を解説
「ブラックリスト」という言葉は、厳密には存在しません。
通常、カードローンの契約や消費者金融での借入れをした情報は「信用情報機関」に登録されています。
信用情報機関とは、個人の金銭的な取引を記録する機関のことです。
サービスを提供する金融機関が、個人の金銭における信用状況や過去のトラブルを調査できるよう、中立的な役割を果たしています。
支払いが長期間滞ったり、債務整理をおこなったりすると、ネガティブな情報として信用情報機関に登録。
これが、私たちがよく耳にする「ブラックリスト」です。
ブラックリストに載る条件
ブラックリストに載る条件は、以下のとおり。
- 2~3ヶ月以上の滞納がある
- 保証会社が代わりに支払った
- 短期間でクレジットカードを複数枚発行・解約した
- 奨学金の返済が滞っている
- 携帯の割賦金を支払っていない
- 債務整理をした など
基本的に、借金や携帯代・奨学金などの支払いが61日以上続くと、ブラックリスト化されます。
また、家賃滞納の支払いを保証会社が肩代わりした場合も掲載対象に。
任意整理や個人再生・自己破産などの債務整理をした場合も、信用情報機関に登録されます。
上記に当てはまる場合は、ブラックリスト化されている可能性が高いといえるでしょう。
信用情報機関は主に3つある
主な信用情報機関は、以下の3つ。
-
CIC(株式会社 シー・アイ・シー)
-
JICC(株式会社 日本信用情報機構)
-
JBA(全国銀行個人信用情報センター)
機関ごとに登録する情報が異なるので、下表を参考にしてみてください。
| 【機関名】 | 【主な金融取引の登録情報】 |
| CIC | クレジットカード、携帯電話、銀行、保険、消費者金融、労働金庫 など |
| JICC | 消費者金融、銀行、クレジットカード、保証会社、リース会社 など |
| JBA | 銀行、信用金庫、農協、信用組合 など |
信用情報機関は、さまざまな情報を管理しています。
- 氏名/住所/生年月日
- 勤務先情報
- 融資やクレジット取引の履歴
- 遅延情報
- 借入残高
- 滞納や延滞の記録、
- 債務整理や破産手続きの履歴 など
各金融機関は、新規ローンやクレジットカードの審査・融資の際に、信用情報機関の情報を確認して個人の信用状況を評価します。
よって「ブラックリストに載る」状態になると、新たなローンの申込みやクレジットカードの新規発行が困難になることも。
信用情報を正しく管理してもらうためにも、返済や取引を適切におこなうことが重要です。
信用情報は時間とともに更新されるため、過去のネガティブな情報が消えることもあります。
ですが、個々のケースで異なるため、消失期間は一定ではない点に注意しましょう。
ブラックリストが確認されるのはどのようなとき?

各金融機関が、信用情報機関に登録された個人情報を確認するのは以下のようなときです。
- クレジットカードの発行
- ローンの審査
- 携帯電話の契約
- 賃貸契約の審査 など
このように、個人の金銭における信用が求められる場面で利用されます。
情報確認の目的は、申請者が過去に返済を滞らせたり、破産手続きをおこなったりしていないかを確認するため。
信用情報機関は個人の信用履歴や取引状況を収集・管理し、各金融機関に提供することで、適切な信用判断をサポートしています。
金融機関は知り得た情報から、利用者の信用リスクが高いか低いかを判断し、審査の結果を決定するのです。
そのため信用情報は、私たちの日常生活に密接に関わっている重要な要素といえるでしょう。
ブラックリストに載ることがもたらす影響とは?
「ブラックリストに載る」状態では、金融機関からの借入やクレジットカード発行が難しくなります。
また、住宅ローンや分割払いも通常は認められません。
さらに、家賃や光熱費などの支払いがクレジットカード引き落としの場合、適応されずに現金での支払いが求められることも。
ブラックリスト化された情報は、一定の期間と条件を満たせば消失します。
各信用情報機関によって異なるので、下表で確認をしましょう。
▼ブラックリストが消えるまでの期間
| 【機関名】 | 【長期の延滞】 | 【債務整理】 (任意整理・個人再生の場合) |
【自己破産】 |
| CIC | 完済から5年 | 5年 | 5年 |
| JICC | 契約継続中または
終了後から5年 |
契約継続中または
終了後から5年 |
契約継続中または
終了後から5年 |
| JBA | 完済から5年 | 5~7年 | 決定日から7年 |
一般的に、ブラックリストの情報が消えるまでには5~7年ほどかかります。
情報の消失までは、新規の借入れやクレジットカードの発行が難しくなりますが、掲載が永遠に続くわけではありません。
ブラックリストに載っても、社会的な信用すべてが失われるわけではないので安心してください。
手元にあるお金だけで生活する意識が養われることで、健全な生活を送るチャンスが生まれるともいえます。
また、ブラックリストの情報は、金融機関と本人以外には開示されないため、第三者に知られる心配もありません。
まとめ
この記事では、ブラックリストの定義や掲載の条件・どのような状況で使用されるのかを解説しました。
ブラックリストは、信用情報機関にネガティブな情報が記録された状態を指し、各金融機関が個人の信用判断をおこなう際に参照されます。
ブラックリストに載ると、新規の借入れやクレジットカード発行が難しくなりますが、社会的信用すべてが失われるわけではありません。
信用情報は時間とともに更新されるため、過去のネガティブ情報は一定期間経過すれば消えていきます。
今回の記事を通して、ブラックリストに関する誤解が解け、正しい知識を身につけることができたら幸いです。
当コラムを運営する「借金トラブル119」では、借金に関する無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用してご自身の借金問題を解決してください。
依頼者に寄り添ってくれて専門家が誠実に対応してくれる借金トラブル119番へお問い合わせください。